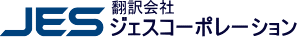Column
| 第51回 代替肉について |
||||||||||||||||||||||||
| <質問> 先日、気の知れた友人と居酒屋に行ったとき、肉料理の話題になったのですが、その友人は「ビールのつまみにするなら高級な肉よりもジャンクな謎肉のほうがいいかも」と言うのです。 「謎肉って、カップヌードルに入ってる、アレ?」 「そうそう!世界中が食料不足になって本物の肉が超贅沢品になれば、合成した肉が当たり前になる時代が来るかもしれないよ」 「そう言えばカニカマは蟹ではないよね。そもそも謎肉っていったいなにでできているんだ?」 こんな話題で盛り上がったのですが、これから先、庶民の口に入る肉は、いったいどうなっていくのでしょうか? やはり人工的に合成された食材が増えていくのでしょうか。(東京都 F.K.)
|
||||||||||||||||||||||||
| <回答> 気をつけてください、熱中症! F.K.さん、ご質問ありがとうございます。すっかり暑さが身に沁みますね。先日、私、屋外で熱中症(heat stroke)になってしまいまして、生まれて初めて失神しました。エレベーターと手押し台車を使って、マンションの廊下を荷物運びに行き来するお手伝いで3~4時間。油断しました。おそらく、大量の発汗による脱水(dehydration)。そこから血圧低下(hypotension/low blood pressure)で熱失神(heat syncope)だったのでしょう。 もちろん作業中に給水していたのですが、1Lでは全然足りなかったみたいです。幸いなことに日陰での休憩中、かつ壁にもたれかかりながらの失神でしたから、昏倒せずに手と膝の打ち身だけで済み、ほんの一瞬で意識は戻りましたから大事には至りませんでした。 しかし、本コラムの第4回(もう4年前!)で解説した自分自身が体験することになるとは、少なからずショックです。今年の夏の暑さと自身の加齢&体力低下の著しさに、すっかり気落ちしています。読者の皆さんも、マメな給水と休息を心掛けてくださいね。 私も、いつもの夏バテくらいなら、生中やジョッキのハイボールをグビグビと飲み干して、元気を取り戻すところなんですが、流石に熱失神して数日は、晩酌を控えました。なぜなら、私たちの身体がアルコールを代謝するときは、生理的な脱水、つまり体内で多量の水分を使うからです。 皆さんもお酒を飲むと、やたらトイレが近くなったり、翌朝すごく喉が渇いたりしませんか? 体内の生理的な化学反応は説明を省くとして、結果的に、身体が、アルコール代謝した後の残りを排泄したり、新しい水分の補充を求めていたりするわけです。 なので、お酒は、元気なときに楽しみつつ、お水も合間にシッカリ飲むのがベターです。もちろん、さらにトイレが近くはなりますが、飲み過ぎと悪酔い、二日酔いの簡単な予防になります。 ちなみに、居酒屋などでよく耳にする「お通し」ですが、これは関東で使われる言葉であって、関西では「突き出し」や「先付け」と言います。
「謎肉」の正体は? さて、本題です。まずは「謎肉」から。日清のカップヌードルに入ったサイコロ状の具材、美味しいですよね! 私は、あまりカップ麺を食べないのですけど、偶に思い出して、カップヌードルを手に取ることがあります。そういえば、少し前にSNSでも話題になりました。改めて調べると、「謎肉」は、2005年頃に誰かがネットで呟いたフレーズなんだとか。そこから、インターネット・ミーム(注1)として、一人歩きを始めたようです。
2016年には、日清食品が公式に商品化して爆発的に売れ、翌2017年、「謎肉」の正体を明かしました。正式名称は「味付豚ミンチ」、豚肉と大豆タンパク、野菜をミンチにして、フリーズドライ加工したものだそうです。
常温保存でき、お湯に戻すだけで、手軽かつ美味しくいただける。これはすごい発明です。カップヌードルが発売された、1971年当初からの具材だそうですから、今で言う、代替食品(food substitute)の先駆けになるのかもしれません。 代替食品の登場 元々、代替食品は、コピー食品とも称されるように、高価で希少な食材に似せた、他の食材による安価な製造コストの加工品を意味しました。F.K.さんも話題にされた「カニカマ(かに蒲鉾)」の他にも、「マーガリン」や「コーヒーフレッシュ」などは、その代表選手です。 意外かもしれませんが、「発泡酒」や「第3のビール」も、まさに「ビール」の代替食品ですよね。最近は、食物アレルギーや宗教上の理由で避けられる食材や、ヴィーガンなど菜食主義の方たちに向けた代替食品も増えました。代替食品が日本で違和感なく広まっているのは、精進料理由来の和食の一部、「もどき料理」に慣れているからかもしれません。 ところで、最近の代替食品開発には、少し別の意味も加わっています。それは、世界的な食糧事情を見据えたものです。いみじくも、F.K.さんのご友人が話された内容ですが、気候の変動や人口増、農畜産業に利用可能な土地の限界などから、遠くない先、世界的に食糧が不足するだろうことは、既に、多くの分野の専門家たちが指摘しています。特に、今回の話題でもある、食肉です。 一般的には、牛肉1 kgを生産するには、トウモロコシ換算で11 kgの飼料が必要で、同じく豚肉1kgでは6kgの飼料、鶏肉では4kgの飼料が必要と言われます。そして、2022年時点、世界の農地の半分が、畜産飼料の栽培だけで占められていると推定されています。
また、一般的に、経済成長する国や地域では、肉の消費量が増えます(高度成長期の日本でも顕著でした)。今後、世界的な肉の消費傾向は、高まりこそすれ、減少することは考えにくいでしょう。一度、舌が肥えてしまうと、食事の質を下げることは、この上なく難しいはずです。 さらに、もう1つ、環境問題も関係すると言われます。国際連合食糧農業機関(注3)が2010年に出した報告では、畜産業に由来する温室効果ガス(主に、二酸化炭素とメタンガス)の排出量は、世界全体の14.5%もあり、その3分の2が、畜牛に由来します。有名な話ですが、ウシのような反芻動物(注4)の曖気(あいき)、いわゆる”げっぷ”に含まれるメタンガスは、温室効果が二酸化炭素の28倍もあり、その影響の大きさが、よく取りざたされます。
もちろん、畜産業を否定したいわけではありません。しかし、代替肉(meat alternative/meat substitute/mock meat)の導入で、無作為な畜産業の拡大による環境の悪化にブレーキをかけることは期待できるでしょう。ただし、個人的には、地球温暖化と温室効果ガス、そして社会経済の関係には、もう少し丁寧な議論が必要と思います。ただ、これ以上は私の専門を超えますので、環境問題に絡むお話は、ここまでにします。 代替肉(プラントベース・ミート) 実際のところ、代替肉とは、どのようなものなのでしょうか? 代替肉は、大きく2種類に分けられます。1つは植物由来の原料から作られたプラントベース・ミート(plant-based meat)、もう1つは家畜の可食部に由来する培養肉(Cultured meat/cultivated meat)です。 代表的なプラントベース・ミートの原料は、大豆のタンパク質(soy protein)です。大豆は「畑の肉」とも呼ばれるように、良質なタンパク質を豊富に含んでいるからです。その他、小麦のタンパク質(gluten)や、えんどう豆のタンパク質(pea protein)など種々の豆類に由来するタンパク質が原料となります。 一般的には、材料となる植物から抽出・精製されたタンパク質を繊維状に加工することで、肉の食感を再現しています。そして、ミンチやブロック、フィレなど、料理に合わせた形に成形し、製品化しています。
日本では、味噌や大豆製品の食品メーカーであるマルコメ株式会社や、ハム・ソーセージ業界首位の食品加工メーカーである日本ハム株式会社が、プラントベース・ミートの有名企業です。他にも、プラントベース・ミートを専門とする企業が頑張っています。 代替肉(培養肉) 一方で、培養肉ですが……まだまだこれから、でしょう。というのも、普段、私たちが口にする精肉(仕入れた塊肉を商品に加工したもの)の多くは、家畜や家禽の筋肉です。あまりピンとこないかもしれませんが、実は、筋肉を培養するのは、とても大変なのです。 もう少し、詳しく説明しますね。まず、培養とは細胞培養(cell culture)を意味します。そして、培養を繰り返して大量に増やせる細胞は、基本的に自己増殖が可能、つまり無限に細胞分裂できるものに限られます。 自己増殖が可能な細胞の多くは未分化で、主に腫瘍(がん細胞)か幹細胞くらいです(第17回を参照)。筋肉も細胞の組織ですが、皮膚などとは異なり、複数の細胞が融合した、筋線維(myofiber)という、大きな多核細胞(multi-nuclear cell)で構成されています。そして、筋線維は細胞として特殊過ぎるため、細胞分裂できません。これが、筋肉の培養が難しい理由の1つです。 したがって、外傷などで破損した筋肉は再生しないため、傷口は皮膚で塞がっても、元には戻りません。ただし、筋線維の損傷が軽ければ、修復はできます。筋線維の周囲には、衛星細胞(satellite cell)と呼ばれる幹細胞が、分裂と分化を静止した状態で、休眠しているのです。 衛星細胞は、筋線維の異常を察知すると、筋芽細胞(myoblast)に分化します。筋芽細胞は、筋細胞(myocyte)の前駆体、つまり筋細胞に分化する直前の幹細胞です。そして、増殖した筋芽細胞は、筋細胞に分化して、弱った筋線維と融合し、筋線維の機能を取り戻すのです。つまり、筋トレで筋肉が太くなるのは、筋線維を軽く傷つけているから、なのです。筋肉痛の理由も分かりますね。 話を戻しますが、ということは、培養肉を作るには、家畜や家禽の筋肉から、幹細胞である衛星細胞を分離・精製し、これを培養して大量に増やし、筋線維に分化させる必要があるわけです。 利点としては、生産の全てが無菌環境下の作業ですから衛生管理は厳密ですし、家畜を肥育するよりも省スペースかつ短時間(数週間~数か月/肥育は年単位)で作成可能ですから、環境負荷を低減できます。当然ながら、動物の屠殺による犠牲も減らせます。 ただし、相応の設備と試薬(特に、培地)、技術者が必要になりますし、維持と管理を含め、お金がかかります。実際、2013年にイギリスで6週間かけて培養した培養牛肉のミンチで作った、世界初のハンバーガー1個ですが、なんと、お値段は3500万円を超えました(5年がかりの研究開発費込みですが)。 それから10年が経ちました。細胞培養の関連技術は向上していますから、もう少しコストダウンできるはずですが、本来の意味での代替食品というには、かなりの貴重品でしょう。
さらに、第39回で説明したように、今の組織工学(Tissue Engineering)では、人工臓器の培養は、とても難しく、まだ皮膚のようなシート状の構造以外に製品化された技術はありません。つまり、立体的な筋組織、肉本来の食感を再現できる塊肉にまで細胞を培養することは、非常に困難です。 しかし、それに挑戦している日本の企業があります。それは、本コラムの初めに触れた、あの「謎肉」の日清食品です。昨年(2022年)には、1辺が約1cmのサイコロ状で、培養ステーキ肉の作成に成功し、試食もされました。 もちろん、さらに大きな塊肉にまで培養する技術は未知数、まして製品化に至る道筋は遥か先でしょうが、見通しは明るい気がします。謎肉ファンの贔屓目ですかね? 細胞農業への期待 今回は、培養肉を中心に解説しましたが、細胞培養技術を応用した、代替食品や医薬品の製造および産業化を細胞農業(cellular agriculture)と言います。つまり、特定の細胞を培養することで、本来なら畜産や農作で得られる収穫物と同じものを生産するわけです。 細胞農業は、大きく2つに分けられます。1つは「培養した細胞そのもの」を利用すること、もう1つは「培養した細胞の生産物」を利用すること、です。培養肉は前者ですが、歴史的には、後者が先んじて、産業化に成功しています。 その、世界初の快挙は、糖尿病の治療薬である、インスリン(Insulin)の生産でした。かつて、インスリンは、豚や牛の膵臓から精製していたため大量に生産できず、とても貴重な薬品でした。 しかし、分子生物学の興隆で遺伝子組換えが可能となり、微生物にヒトのインスリン遺伝子を組み込むことで、インスリンの大量生産が可能となったのです(1981年)。 現在、日本でも、細胞農業を国家的な産業に見据える動きが高まっています。実は、今年(2023年)の2月に、国会の衆議院予算委員会で、岸田首相が、細胞農業の産業化推進(法的な環境整備)を明言しています。 もちろん、楽観的になるには早過ぎます。けれども、科学技術の発展が将来の産業を橋渡しする、その瞬間に立ち会えるかもしれないと考えると、夢がありますよね。そして個人的な願望としては、研究開発者には、味覚も天然ものに負けないくらい追求してほしいな、と思っています。 |