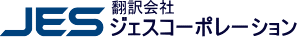Column
| 第54回 麻酔について |
||||||||||||||||||||||||
| <質問> 先日、歯が痛くなって、歯医者さんに行きました。実に、ウン十年ぶりです。小学生のときに泣きながら治療の痛みに耐えて、もう二度とかかるまいと誓っていたので、ものすごく憂鬱でしたが、あのときとは全然違って、全く痛くなかったんです。びっくりしました。 そういえば、少し前に大きな手術をした親戚も、術中はもちろん、術後も全然痛くなかったと言ってました。 本羅先生、今の麻酔って凄いんですね。そもそも、麻酔って、なんで効くんでしょうか。 (神奈川県 S.T.)
|
||||||||||||||||||||||||
| <回答> S.T.さん、歯の調子は戻りましたか? 歯が痛いとゴハンも美味しくないですし、憂鬱になりますよね。 さて、麻酔についてのお話しということですが、本コラムの記念すべき第1回でも軽く触れていました(もう4年半も前ですね)。それで今回、改めて調べてみたのですが、全身麻酔が効く理由は、未だ解明されていないようです。医療に使う、こんな重要な薬が、なぜ効くのか分からないなんて!?と驚きますよね。もちろん、少しずつ、分子レベルで研究は進んでいます。しかし、実は、そもそも、現時点では解明し尽くせない、根本的な問題を抱えているのです(後述します)。 麻酔薬の種類 現代の外科手術では、大きく分けて3種類の麻酔薬を使います。1つめは意識を失わせる全身麻酔薬(general anesthetic)、2つめは痛覚を抑える局所麻酔薬(local anesthetic)と鎮痛薬(analgesic)、そして、3つめに筋肉の収縮を止める筋弛緩薬(muscle relaxant)です。麻酔科医は、手術の内容や患者さんの状態に応じて、この3種類を適切にブレンドしています。この内、全身麻酔薬以外は、なぜ効くのか解明済です。 筋弛緩薬の作用機序 3つ目の筋弛緩薬が麻酔薬と聞いて、違和感を覚える読者もおられるかもしれません。しかし、現代医療の麻酔では、とても重要な薬です。筋弛緩薬は、ざっくり言うと「筋肉が縮むのを邪魔する薬」、つまり、身体を動かなくします。 外科手術では、治療行為として、メスやハサミで患者さんを大なり小なり傷つけます。すると、意識が無くても、強い刺激のために脊髄反射で身体が動くのです。つまり、手術中の患者さんの不意な動きを止めるために、筋弛緩薬が必要なのです。すると、筋肉のカタマリである心臓も止まるのでは?と思いますが、心配には及びません(これも後ほど説明します)。 では、なぜ筋弛緩薬は効くのでしょうか。その作用機序ですが、これは、筋肉が縮むときのメカニズムを知れば理解できます。しかし、そもそも、筋収縮のことを誤解している読者の方が多いかもしれません。意外かもしれませんが、私たちの脳は身体に、「常に筋肉を緩めるように!」と制御しています。実のところ、物質としての筋肉は、ギュっと縮んだ状態が自然なんですね。 死後硬直(rigor mortis)(注1)という言葉を聞いたことのある読者もおられるのではないでしょうか。刑事モノや法医学モノのドラマでよく耳にする、殺人事件の被害者の死亡時刻を推定するために使う知識です。時間とともに死体の筋肉が収縮して、硬化することを意味します。
つまり動物は、生きている間、ずっと筋肉を緩ませるためにエネルギーを使っているのです。「力を入れる」というくらいですから、素朴な感覚としては筋肉を縮めるときにエネルギーを集中しているような気がします。 でも、実際には、緩んだ筋肉のスイッチを入れるだけで勝手に縮むのです。より正確に言うと、筋肉は多くの筋線維の束ですから、筋線維1本1本にスイッチがあり、力の調節は「何個のスイッチを入れるか」ということになります。もう少し比喩的に言うなら、筋線維に含まれる筋原線維は弓矢、あるいはボウガンのようなものです。 筋肉が緩んでいる状態は、弓を引き絞って固定しているのと同じです。なんとも不思議ではありますが、これは、筋原線維の力の源である2種類のタンパク質に秘密があります。それはアクチン (actin)とミオシン(myosin)と言います。繊維状のアクチンにミオシンが結合すると、自動的に、ミオシンはアクチン線維の上を決まった方向に滑走する性質があるのです(注2)。
言い換えると、「筋肉を緩める」ことは「エネルギーを使って、アクチン繊維からミオシンを引きはがす」ことで、「筋肉を伸ばす」ことは「アクチン繊維を滑走する方向と逆の端に、ミオシンを少し離して設置する」ことになります。 弓を引いたままで待機するなんて、考えるだけで疲れます。それが、筋肉のレベルでは「力の入っていない」状態、私たちが生きてボーっとしているときなのですから、逆説的に聞こえて、面白いですよね。ちなみに「足が引きつる/こむら返り」は、冷えなどで末梢の血流が滞って、筋肉が一時的にエネルギー不足になったために起こります。 ある意味では「死後硬直もどき」と言えるかもしれません。ですから、対処法として「引きつれた筋肉を伸ばして温める(血行を良くする)」わけです。 というわけで、ド根性モノのマンガやアニメによくある「これが俺の120%の力だっ!」と叫ぶシーンも、筋肉レベルでは「筋線維のスイッチ・オン!」で、引いた弓の戻るが如く縮むだけですから、生理学的には「筋線維の数」以上の力は発揮できません。実も蓋も無い話で、ごめんなさい。 その筋線維のスイッチは「神経-筋接合部」と言い、脳からの指令が筋肉に伝わるところです。脳からの指令は神経線維を電気信号で伝わり、神経線維末端となる「神経-筋接合部」の神経側、シナプス前終末(presynaptic terminal)から伝達物質(transmitter)が放出されます。そして伝達物質が、筋肉側の細胞表面にある受容体(レセプター(receptor))に結合することで、筋収縮のスイッチが入ります。 筋収縮に限らず、これは生命活動において一般的かつ重要なメカニズムの一つです。まず、伝達物質と受容体は「鍵と鍵穴」の関係にあります。さらに、受容体は「鍵穴でありスイッチでもある」とイメージしてください。 ある伝達物質(鍵)は、形の合う特定の受容体(鍵穴)に刺さります。そして、受容体は特定の細胞機能と紐づいていて、形の合う伝達物質が刺さると、その細胞機能にスイッチを入れるのです。「神経-筋接合部」で鍵の役割をする伝達物質は、アセチルコリン(acetylcholine)です。そして、鍵穴のアセチルコリン受容体に刺さり、筋収縮のスイッチがオンになります(図1)。 筋収縮のメカニズムをこのように理解すると、筋弛緩剤の作用機序も簡単に分かります。ようするに、筋弛緩剤は、アセチルコリンの偽物なのです。偽物の鍵が鍵穴に刺さって、スイッチが入らない、とイメージしてください。つまり、本物の鍵(アセチルコリン)が刺さる邪魔になるので、結果的に、筋肉の縮むスイッチが入らないわけです。 ちなみに、ここで先の宿題を一つ終わらせておきましょう。心筋を拍動させる伝達物質は、ノルアドレナリン(noradrenaline)といいます。したがって、アセチルコリンの偽物である筋弛緩薬は影響せず、心臓は止まりません(注3)。ご安心ください。
オピオイドとその作用 次に、鎮痛薬の一部、オピオイド(Opioid)と呼ばれる一群の物質について、です。その作用機序は、筋弛緩薬と同じ説明ができます。つまり、オピオイドは、神経細胞のオピオイド受容体に作用して、神経細胞の活動を抑制させるのです。オピオイドはオピウム(opium)類縁物質という意味で、オピウムとは芥子(opium poppy)の実の果汁を乾燥させたもの、要するに、アヘンのことです。つまり、オピオイドとは、「アヘン」や、アヘンの成分を精製したモルヒネ(morphine)の類、さらに加工したヘロイン(heroin)の類、そしてモルヒネやヘロインに似せて合成した化合物の総称です。いわゆる麻薬(narcotic, (注4))の一種とお考えください。
アヘンは、古くから人類史に記載されるほどポピュラーな存在でした。考古学的には、紀元前5千年に遡る種子が見つかっているのだとか。では、なぜ植物に由来する物質であるオピオイドが、私達の身体の内側、それも神経細胞にある鍵穴に刺さるのでしょうか。 理由は、簡単です。私達の神経細胞、そして神経細胞のネットワークである脳というシステムが、元々、オピオイドを伝達物質として使っているからです。神経伝達物質の一種である、内在性のオピオイドをエンドルフィン(endorphin)と言います。エンドルフィンは、動物が生まれ持つ鎮痛作用(analgesic action)や多幸感(euphoria)に関わります。 まさに「脳内で分泌されるモルヒネ」です。俗に、体内麻薬と呼ばれることもありますが、特に、本能的な欲求(食欲/睡眠欲/性欲/生存欲)が満たされるときに、分泌されると考えられています。 「生存欲」の分かりやすい例は、いわゆるランナーズハイ(runner's high)が当てはまります。ランナーズハイは「長時間のマラソンなど、継続的な運動による苦しみを我慢した先に気分が高揚する」という現象です。これに、エンドルフィンの分泌が関与しているのです。 少し話はズレますが、違法薬物としての「麻薬」と「覚醒剤」の作用は、それぞれ「沈静」や「興奮」と、似て非なるものです。しかし、なぜ脳に効くのかといえば、どちらも「神経伝達物質の偽物」だからです。 中枢神経系を刺激する薬物には、それぞれに対応する本物の伝達物質と、それらの結合する受容体があります。いつもなら、本物の伝達物質と受容体が、私達の脳を正常に機能させています。そこに偽物が混入することで、脳の機能である心に作用するわけです。 ただし、筋肉の場合と異なり、こちらは本物より強くスイッチを押す薬物もあり、いずれにせよ神経細胞に異常な反応を起こします。ちなみに、広い意味では、タバコのニコチン(nicotine)やコーヒーのカフェイン(caffeine)も、「神経伝達物質の偽物かつ毒物」です。要するに、嗜好品とは「すべからく身体に悪いもの」なのでしょうね。まぁ、ほどほどに楽しみましょう(と、自戒を込めつつ)。 閑話休題。オピオイドの他にも、鎮痛薬はあります。オピオイドが中枢神経系に作用して「痛みの感覚」を遮断/緩和するのに対し、いわゆる市販の「痛み止め」は「痛みの大元である組織の炎症」を抑えることで「痛むこと、そのもの」を和らげます(「治療」ではなく、一時しのぎではありますが)。 その主成分は、非ステロイド性抗炎症薬(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs:エヌセイズ/エヌセッズ)と言い、「解熱鎮痛剤」と表記されていることが多いでしょう。古くはアセチルサリチル酸(acetylsalicylic acid)、いわゆるアスピリン(独: Aspirin)ですね。 最近の市販薬でメジャーなものだと、イブプロフェン(ibuprofen)やロキソプロフェン(loxoprofen)でしょうか。いずれにせよ、NSAIDsは、何らかの影響で組織が発熱や炎症を生じるときに、それら発熱や炎症を仲介して広げる物質の合成を抑制します。 実は、この作用機序も「鍵と鍵穴」で説明できます。つまり、炎症を広げる物質を合成するときに必要な「伝達物質と受容体」の結合を偽物であるNSAIDsが邪魔して、発熱や炎症の発症を抑える、という訳です。 局所麻酔と神経系 一方、痛覚を抑える、もう一種類の薬物である「局所麻酔薬」は、オピオイドと同じく、神経細胞に効いていますが、作用機序は異なります。ここで、ざっくり神経細胞の機能をまとめると、次のようになります。 1. シグナルとして、伝達物質を受け取る(細胞への刺激)。 2. それを「細胞膜の電圧(膜電位)」か「細胞内の化学反応」に変換する(刺激の蓄積/減少)。 3. ある刺激量(刺激の閾値)に達すると、シグナルを別の細胞に伝えると決める(興奮)。 4. シグナルを別の細胞に伝えるために膜電位を電気信号(注5)に変換する。 5. 電気信号が細胞表面を伝わり、シナプス前終末(注7)から伝達物質を放出する。 6. 1に戻る。
オピオイドが、上記した「神経細胞の機能1」を邪魔していたのに対し、局所麻酔薬は「機能4」を邪魔します。もう少し具体的に説明すると、(注5)で解説したイオンチャネルが開くのを妨げているのです。すると、神経細胞が電気信号を作れず(興奮できず)、痛みの刺激を伝えられなくなる、という訳です。 現代科学において「薬が効く」と言うときは、その薬が「どんな形(分子構造)をしていて、どこに作用するのか(標的)」が分かっていることを意味します。ここまで見てきたように、筋弛緩薬や鎮痛薬が効く理由は「鍵と鍵穴」の関係、つまり、鍵穴である受容体(標的)に刺さる分子構造を持った偽物の鍵が、それぞれの薬であると説明できますし、「イオンチャネルが開くのを邪魔する」ような物質が局所麻酔薬になります。 分子構造から薬をデザインするような薬品開発の理想は、薬に求められる作用を逆算した分子構造を合成することです。もちろん、そのためには「薬が、どこに(標的)、どのように作用するのか(薬理作用)」を完璧に近い精度で知らねばなりません。もちろん今はまだ、そこまで自由自在ではありません。通常の薬品開発は、「標的の研究」と「薬理作用の研究」の両面から攻めます。 全身麻酔と意識の関係 まず、経験的に使われてきた薬品分子の構造や性質を調べます。言ってみれば、色んな薬を化学的に分解して比べながら「分子構造の、どの部分が効くのか?」を研究するのです。ところが全身麻酔に使われる薬には、なんと「共通の分子構造」がありませんでした。 分子の形がバラバラだと、どんな構造が全身麻酔に効くのかを比べられません。つまり、薬理作用のヒントを見つけられないのです。 分子構造に特徴が無いということは、全身麻酔薬の薬理作用に分子の形は関係ないのかもしれない。形に関係なければ、特定の何かに結合するのではなく、むしろ「どこにでも付く/場所に関係なく付く」のかもしれない。もっと大きな特徴があるはずだ。
そんな大胆な考えが、全身麻酔薬の研究を大きく進歩させました。全身麻酔薬には、ある化学的な性質が共通していたのです。それは脂溶性(油に溶けやすく、水に溶けにくい)でした。実際、実にキレイな法則性があります。それは、「脂溶性の高い薬ほど、少量で麻酔が効く(つまり麻酔効果が強い)」ということです。 では、脂溶性が、どのように麻酔効果と関係するのでしょうか。まず、代表的な仮説として、「全身麻酔薬は細胞膜に影響している」と考えられました。細胞膜は脂質で作られていて、その構造は脂質二重層と言います。つまり、脂溶性が高いと細胞膜に薬が溶けやすいわけです。しかし、薬が細胞膜に溶けたとして、「どのように神経細胞に影響するのか」が分かりません。 詳しく実験していくと、どうやら、脂溶性の高さと麻酔の強さの関係には限界があると分かりました。実は、麻酔薬の分子の形や大きさも微妙に関係しているようです。さらに、細胞膜のどこにでも麻酔効果があるとは言えないようです。 つまり、特定の場所(鍵穴)に特定の形(鍵)というほど厳密ではないけど、大雑把な感じに作用しているのです。言い換えると「鍵と鍵穴の関係説」と「細胞膜に高い脂溶性の薬が溶ける説」の良いトコ取りです。 ざっくり説明すると、細胞膜に存在する受容体やイオンチャネルの脂溶性の部分に麻酔薬が割り込んで、受容体やイオンチャネルの邪魔をしているのではないか、ということです。受容体やイオンチャネルは、そこそこ大きな分子なので、細部には水溶性と脂溶性の部分が混在しています。 その脂溶性部分に全身麻酔薬が溶けて、受容体やイオンチャネルの形を歪めたり、塞いだりするのかもしれません。 全身麻酔薬が神経細胞の「どこに、どのように作用するのか」は、そう遠くないうちに分かるでしょう。しかし、ここから、冒頭で予告した「現時点では解明し尽くせない、根本的な問題」が、顔を覗かせます。それは、全身麻酔薬によって失われる「意識」についてです。 現時点で、科学は「意識のメカニズム」を解き明かしていません。筋肉のメカニズムが分かるから筋弛緩剤の作用機序が理解できるように、全身麻酔薬の作用機序、意識消失に至る理由を完全に理解するには、意識のメカニズムを解明する必要があるでしょう。 脳は神経細胞の塊なので、神経細胞が正常に働かないことが全身麻酔薬の作用機序の一部だとすれば、意識消失の入り口は見えているのかもしれません。しかし、大きな枠組みに過ぎませんが、実用上として、例えば、救急医療で使われているコーマ・スケール(Coma Scale)という「意識障害の評価基準」はあります(図2)。 この場合は「意識のレベル」を刺激に対する反応として外からわかる範囲で評価しています。この、それぞれのレベルで、脳内に起きている現象を記述できるようになることが、まずは目標だと思います。
未解明の領域と今後の研究方向 究極のところ、全身麻酔薬が「意識を消失させる」作用機序が解明できない理由は、「意識」のメカニズムが謎だからです。一方で、全身麻酔薬と意識の謎が対になるのなら、全身麻酔薬の研究が進むことで、意識のメカニズム解明に繋がるかもしれません。そう考えると、麻酔の研究は、意外な可能性を秘めている、とも言えます。なかなか面白いと思いませんか? |