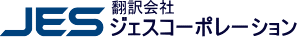Column
| 第76回 抗菌薬と薬の歴史(前編) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <質問> 本羅先生、こんにちは。この間、いつも元気いっぱいの祖母が、何年ぶりか分からないほど久しぶりに風邪気味で、まさか新型コロナに感染したか、いや百日咳か!?と、慌てて病院に連れて行きました。幸いにも色んな検査は全て陰性で、ただの風邪だったようです。ホッとしました。 処方箋をいただいて、薬局に立ち寄った帰り、どうも祖母がプリプリと怒っていて、「どうしたの?嫌なことあった?」と尋ねると、 「なんだい、あの病院の先生は。薬を出すのをケチってんじゃないかねぇ。全然、少ないよ。ほら、抗生物質とかさ、解熱剤とかさ、何もないじゃない。昔は、もっといっぱい薬を貰ったのよ?」 と、まくし立てました。私が、 「えぇ、何それ!? おばあちゃん、そもそも、そんなに熱は高くないよね(苦笑)。薬もタダじゃないんだし、飲まずに済むなら、その方が良くない? 」 と答えたのですが、イマイチ納得いかないようで、ブツブツ言いながら帰宅しました。ていうか、おばあちゃんの若い頃は、風邪くらいで、そんなに、お薬たくさん出ていたんですかねぇ……。むしろ私は、あまり飲みたくないのですけど。 そういえば、本羅先生はコラムでお薬の飲み方を注意されていましたね(第74回)。お薬の話、もう少し詳しく聞いてもいいですか?(東京都 I.K.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <回答> I.K.さん、ご質問ありがとうございます。おばあ様、酷い病気でなくて何よりでした。あまり発熱していないとのことですが、まだまだ暑い日が続いていますし、脱水に気を付けて、マメな給水を心がけてください。くれぐれも、エアコンを切って暑さを我慢するようなことはせず、かと言って、身体を冷やし過ぎず、快適な室温で安静になさってください。すでに病院の先生から、お聞きになっているとは思いますが……。 ちなみに、無料の意味で使う「ただ」は、漢字で書くと「只」。元々は「たった一つの/そのままの」という意味です。「ただ~するだけ」という使い方の内、「ただ」モノを貰うだけ、「ただ」食事をするだけ、という「料金を払わない状況」が語源になっているようです。俗に「ロハ」とも言いますが、これは漢字を分解して片仮名で読んだわけですね。 風邪薬と対処療法 ところで、おばあ様のご機嫌が斜めになってしまった「風邪薬」についてですが、そもそも風邪(普通感冒(かんぼう)、かぜ症候群)には、特別な治療法がなく、基本的には、対症療法(symptomatic therapy)として「服薬」「滋養」「安静」で体力を回復するしかありません。 改めて、対症療法とは「疾病に伴う多様な症状の緩和処置」であり「病因の治療」ではありません。風邪の諸症状には、発熱/頭痛/炎症などを抑える解熱鎮痛剤(Antipyretic analgesic)、くしゃみ/鼻水を抑える抗ヒスタミン剤(antihistamine agent)、咳を止める鎮咳剤(antitussive medicine, ちんがいざい)、痰の排泄を促す去痰剤(expectorant, きょたんざい)、それらを補佐して呼吸を楽にする気管支拡張剤(bronchodilator)が処方されます。これらの各薬剤を配合し、1つにまとめた医薬品が総合感冒薬(general-purpose cold medicine / multi-ingredient cold medication / combination cold remedy)です。 おそらく今回、おばあ様への処方は、総合感冒薬だけだったのではないでしょうか。それで足りるくらいに症状が軽いと、診断されたのでしょう。 6年前の本コラム第7回で説明したように、風邪の原因は、ウイルスです。おそらく、おばあ様は「抗生物質は細菌に作用する薬で、ウイルスに効かないため、風邪薬に使わない」ことをご存じないのかもしれません。ただし、おばあ様が存じ上げないことは、やむを得ない面もあります。実は、かつて一部の医師が「細菌の二次感染(注1)を防ぐ」という名目で、風邪の患者に無意味な抗生物質を気軽に処方していたのです。
後述しますが、公衆衛生を害する愚かしい行為です。一部とはいえ医師がこうでしたから、おばあ様を含め、一般の方では、なおさらでしょう。 人類と薬の出会い ― 霊長類にも見られる“自己治療” そもそも素朴な意味で、私たち人類は、どのように薬と付き合ってきたのでしょうか。それこそ、医学/薬学という言葉どころか、何も無かった、遥か悠久の彼方。もしかすると、学名ホモ・サピエンス(Homo sapiens /ラテン語で「賢いヒト」)と呼ばれる存在に進化する前から、私たちは、薬と共に存在していたのかもしれません。 なんだ、なんだ?!そんなファンタジー(fantasy, 幻想的、超自然的)めいた話を始められても困るぞ、と訝しがる(いぶかしがる)のは、少しお待ちを。 実は、チンパンジー(Chimpanzee /学名:Pan troglodytes)やオランウータン(Orangutan /学名:Pongo)、アカコロブス(Red colobus /学名:Procolobus badius)といった、現代におけるヒト以外の霊長類が、食用とは別の植物を薬っぽく摂取しているのです。たとえば、体調不良(腹痛 / 食欲不振 / 下痢・便秘)のとき、いつも滞在している果樹の上から、わざわざ離れ、普段は見向きもしない草木を探して口にすることもありますし、怪我の治りが遅いときには、また別の草木を噛み、汁を指に取って膿んだ傷口に塗るというのです。
面白いことに、いつもなら満足そうに食べる表情が、薬用植物をモグモグしながら明らかに嫌そうな顔をしています。まさに「良薬口に苦し」でしょうか。ちなみに、英語でも”Good medicine tastes bitter.”と言いますね。洋の東西を問わず、全く同じフレーズ(phrase)で、かつ同じ「忠言/諫言の比喩(ひゆ)」であることに、少し驚きます。 古代中国の医薬と「本草学」の誕生 閑話休題。賢いおサルさんに出来ることですから、万物の霊長(the lord of creation)たるヒトも負けてはいません。アレコレと口にしては、試行錯誤してきたのでしょう。 1~2世紀に編纂(へんさん)された、現存する中国最古の本草書(医薬品の解説書)である「神農本草経」、この本に冠せられる「神農(注2)」は、医/薬/農/商を人々に伝えた神様だそう。伝説では、あらゆる本草(注3)を口にして、自身の身体で薬効と毒性を試したとか。なんと身体を張った神様でしょう。
日本への伝来と本草学の展開 様々な本草書は、奈良時代以降の日本に、遣隋使や遣唐使、後には商船を通じて各時代に輸入されました。もちろん医薬品の解説という実用もさることながら、むしろ百科事典や図鑑のようにも扱われました。つまり、日本における本草学は、西欧で言う博物学(Natural history, 本コラム第65回参照)に近く、広い意味での自然科学だったのです。ちなみに、本草学における動物の分類は、大きく「人間」「獣」「鳥」「魚」と「虫」で、「虫」には「昆虫」の他、「爬虫類」「両生類」「甲殻類」が含まれます。実は、ヘビ(蛇)/カエル(蛙)/エビ(蝦)/カニ(蟹)など、動物を意味する漢字の部首に「虫」が多く使われるのは、本草学の分類に由来するのです。 ブランド志向(brand consciousness)が強い、貴族中心の平安時代までは、海外(主に「唐」)の知識が重用されました。日本で、中国の方士に相当するのは、陰陽師(おんみょうじ)。医師や薬師と並び、宮廷における重要で特殊な役職です。映画や小説などの題材としても有名ですね。個人的には大好きな話題ですが、本題から外れるので、ここでは掘り下げません。 日本の医学と薬学は、遣唐使の廃止された室町時代(武士中心)から、わが国の風土や気候に合わせて工夫されるようになったと思われます。 漢方薬とその注意点 時を経て、江戸時代。オランダを通じた西欧の学問/文化、「蘭学」が広まり、本格的に西欧の医学(蘭方)と博物学が流入して、本草学と混交します。それに呼応して、伝統的な「日本独自の医学」は「漢方」と呼ぶようになりました。意外かもしれませんが、漢方は、「伝統」というには新しい、江戸時代にできた言葉で、漢方薬も、実は日本で独自に発展した医薬品なのです。確かに起源は同じ古代中国ながら、漢方は、中医学(中国)や韓医学(韓国)と異なる医学体系です。もちろん、生薬(漢方薬の薬効成分)の配合も中医/韓医とは異なります。ついでながら「民間薬」も漢方薬とは別です。室町時代から僧医などを通じて広まりました。実は江戸時代に、水戸黄門こと、徳川光圀(みつくに)公の勅命で、書籍「救民妙薬(きゅうみんみょうやく)」にまとめられています。 いずれ「現代の医薬品より安全」と思われるかもしれませんが、薬である以上、漢方薬にも副作用は必ずあります。近年、特に美容関係で「手軽で安心/すぐに効く」とインターネットで広告される漢方薬が出回りますが、診察も無く専門医から処方されない、特定の効能を標榜する薬は、基本的に毒と同じです。安易に服用するのは危険です。お気をつけください。 先史時代の外科治療と医薬の痕跡 さて、人類と薬に話を戻して、遠い過去へと目を凝らせば、フランスで発掘された、紀元前7000年(新石器時代)の遺跡から、農民の左前腕切断手術跡が発見されたと2007年に報告がありますし、2022年には、なんと3万年以上も昔を生きたボルネオ島(インドネシア)の若者が、左脚を1/3も外科的に切断して10年近く生存していたとの発掘研究が、世界的な論文誌”Nature”に掲載されました。
3万年前ともなれば、刃物と言っても、鉄や青銅すら無く、せいぜい磨製石器(注4)で、広大な草原で巨大なマンモス(mammoth)と戦う時代。しかも、場所が熱帯雨林気候です。現代でも切り傷からの感染症が問題となる、草木の鬱蒼と生い茂る蒸し暑い地域で、そこまで高度な外科治療ができるとは! 高度に医術/薬物を使いこなしていたであろうことに戦慄します。
ここからは、歴史に沿って、人類の文明と薬の関わりを順に見ていきましょう。
古代文明と医薬の発展 人類最古と称される「古代メソポタミア文明(注5)」の遺跡からは、すでに薬局が確認でき、紀元前2000年頃に刻まれた楔形文字(注6)の文書には、動植物や鉱物を素材とする医薬品の調剤と処方が多く記載されています。また「古代エジプト文明(注7)」の様々なパピルス(注8)に記載される、同様の医薬に関する記述は、紀元前3000年に遡ります。 一方、紀元前2600年に栄えたインダス文明(注10)は、公共浴場や排水システムの整った、公衆衛生が強く意識された都市計画で知られていますし、紀元前1000~500年にはインドの伝統医学「アーユルヴェーダ(注11)」が編纂されました。「アーユル(Ayus)」は、サンスクリット語(注12)で「寿命/生気/生命」を意味し、「ヴェーダ(veda)」は「知識」を意味するバラモン教の経典/文献です。複合語「アーユルヴェーダ」を今風に訳せば「生命科学」でしょうか。伝統医学とはいえ、内科/外科の他、今でいうアンチエイジング(anti-aging, 抗加齢)や予防医学(preventive medicine)に類する考え方まで含む、驚きの医学体系です。もちろん医薬品とする動植物や鉱物の記述も多く、扱う薬草だけで数千種類。投与する患者に合わせ、薬を溶かす液体(茶/乳/油脂/酒)や剤型(錠剤/丸薬/粉末)を変えることが特徴です。
ギリシア・ローマの医学 ― ヒポクラテスからガレノスへ メソポタミアから西に目を向けると、地中海東岸のエーゲ海(Aegean Sea)では、古代エジプト文明の影響を受けた、古代ギリシア文明(注14)が開花しました。ここで、ようやく現代につながる扉が開きます。「医学の父」ヒポクラテス(Hippocrates)の登場です。とはいえ、紀元前4世紀と、少し後の時代ですが。
ここまで人類は様々に薬を使ってきましたが、実際の医術としては、宗教にまつわる祈祷(きとう)/呪術/迷信の延長に過ぎない面が多々ありました。そこから現代の「医学」に道を切り拓(ひら)いたのがヒポクラテスです。疾病を生物学的な過程と考え、患者の臨床症状と経過観察を重視し、自然治癒力の棄損を避け、回復を促すことを基本とする医術でした。 昔から知られる薬の多くは経験的に選抜され、数百程度に整理されました。ただし、当時のギリシアでは遺体の解剖は忌避/禁止され、人体の解剖学的/生理学的な知識の正確さは望むべくもありません。呪術や迷信からは開放されましたが、「血液/粘液/黄胆汁/黒胆汁の不調和が疾病」という四体液説(humorism)に沿った診断のため、一定の治療効果は認めつつ、現代の医療とは程遠いものです。 しかしながら、当時、最先端の医学です。ヒポクラテスの影響は強く、後進の教育に熱心だったこともあり、多くの弟子が育ちました。 時代が、古代ローマ(注16)に移っても、文化的には、ずっと古代ギリシアが優勢でした。当時の世界、全体の文化を融合していますからね。実際、西暦1世紀頃のローマ皇帝に仕えた、「薬理学と薬草学の父」ペダニオス・ディオスコリデス(Pedanius Dioscorides)は、今でいうトルコ南部の出身ですが、19世紀まで西欧/イスラム世界で基本かつ最重要な薬学文献となる名著「薬物誌(ラテン語:De materia medica, デ・マテリア・メディカ)」をギリシア語で執筆しています。 古代ローマで最も偉大な医師の一人である、西暦2~3世紀のガレノス(Galen, ラテン語:Galenus)もギリシア語で話し、執筆しました。彼は外科医として、剣闘士(Gladiator, 剣奴:見世物として戦う奴隷/相手は猛獣や奴隷同士)養成所で負傷者の治療から人体の仕組みを学び、動物を解剖して研究しました。特定の学派に属さず、古代ギリシアの医学を体系的にまとめ、特に、ヒポクラテスの医学とペダニオスの「薬物誌」を高く評価し、後の世に繋げました。
ところが、ガレノス以降、古代ローマの衰退とともに、古代ギリシアの学問が失われ、中世の医学は停滞しました。ヒポクラテスの開いた「医学」の扉は閉ざされ、医療は、宗教施設と地域ごとの民間療法が中心となります。宗教施設が地方文化の中心となり病院を併設、ヒポクラテス医学の文献こそ残されましたが、新たな知識を受け入れない、悪い意味で保守的な、形式にこだわるだけの理念的な医術は、ヒポクラテスの理想とは真逆と言えます。こうした状況が覆されるのは、時代が進んで近代科学の発展を待たねばなりませんでした。 と、これでも、かなり端折ったつもりなのですが、さすがに字数が嵩張り過ぎましたね。以降の歴史、近世/近代/現代の薬学事情、特に抗菌薬の開発については、次回に解説したいと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||